相続と時効のお話 その2
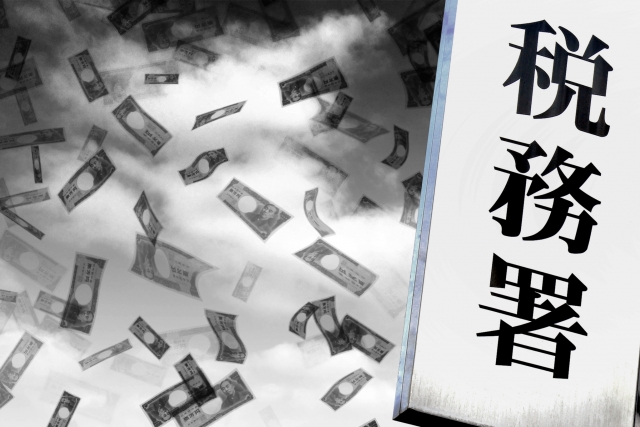
相続発生後に相続人などが行う手続きは多岐にわたり、その期限が定められていないものもあれば、期限内に行わなければ権利等を失うものもあります。前回に引き続き、相続に関する様々な手続きや権利のうち、おもに知っておきたい時効・期限についてお伝えします。
■特別の寄与に関する申立は「6か月または1年」
前回お伝えした「遺留分侵害額の請求」と同様に、改正民法が施行された2019年7月1日以降に発生した相続について申立てが可能です。
改正前から「寄与分」の規定は存在していて、
「被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者」
には、本来の相続分に寄与分を加えた額を相続分とする、となっていましたが、寄与分は相続人だけに認められている制度でした。
たとえば被相続人の子の妻が、生前に被相続人の介護や身の回りの世話などを無償で行っていた場合には、その妻は相続人とはならないため、寄与分は認められずに、被相続人の財産を相続することができません。
このように相続人以外の親族(特別寄与者)が被相続人に対して
「無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与」
をした場合に、相続人に対して「特別寄与料」を請求できるように制定されたのが「特別の寄与」です。
なお特別の寄与の申立てができる特別寄与者は、民法で定められている次の親族となります。
1.六親等内の血族(血縁関係がある者)
2.配偶者
3.三親等内の姻族(【例】自分と、配偶者の父母・兄弟姉妹・叔父叔母との関係)
このうち配偶者は、相続人となり血族も相続人となり得るため、特別の寄与は姻族の生前の寄与に対して制定された制度と言えます。「被相続人の子の妻」であれば被相続人の一親等の姻族となるため、申立が可能となります。
特別寄与者が相続人に対して特別の寄与料を請求し話し合いが行われ、解決しない場合には特別寄与者が家庭裁判所へ調停の申立を行うことになります。
裁判所は「寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮」して特別寄与料の額を定めることとなっていますが、話し合いの段階で寄与料をいくら請求するのか、また裁判所がどのように寄与料を算定するのかはケースバイケースとなります。
ただし、このような制度が創設されたため、親族に特別寄与者となり得る人がいるかどうか、親や自身等の相続に当てはめて確認しておくことが必要となります。なお特別寄与料を支払うことになった場合には、相続人は法定相続分に応じて負担することになります。
■相続税は「10か月と5年」
1.相続税の申告
相続税の申告は、「相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内」に申告・納税を行うこととなっています。遺言書がある場合にはその内容に沿って、無い場合には相続人間の遺産分割協議によって財産を相続します。
相続税の課税対象となる財産は、被相続人から相続、遺贈によって取得した財産の他、相続時精算課税の適用を受けた財産、7年以内に暦年贈与された財産が含まれます。また、生命保険の死亡保険金や死亡退職金も「みなし相続財産」として課税対象となります。
この財産から債務、葬式費用、非課税限度額内の死亡保険金等の非課税財産を差し引き、さらに「3,000万円×法定相続人の数」の基礎控除を差し引いた額が課税対象となる財産の総額となります。
この財産を法定相続分で相続したとして計算をして、相続税の総額が決定します。その後、相続税の総額を、実際に相続した財産額の割合で按分して、各相続人の相続税額が算出されます。この税額から配偶者控除、未成年控除等の控除を行い、実際に負担する税額が決定します。
なお相続税の申告は、遺産分割協議が調わない場合にも10か月以内に行う必要があります。その場合には、法定相続分で相続したとして申告する必要がある他、「配偶者控除」や「小規模宅地等の特例」等が適用できないため、一時的に税負担が大きくなる可能性があります。
2.相続税の更正の請求
前述の「遺産分割協議が調わない場合」の更正の請求は、遺産分割が完了した日の翌日から4か月以内、配偶者控除等特例の適用ができるのは、原則として申告期限から3年以内に遺産分割が完了した場合に限られます。請求をすることによって、多く申告した税額の還付を受けることができます。
それ以外の更正の請求は、相続税の申告期限から5年以内となっています。相続財産のうち、特に土地の評価は複雑となり、実際の評価額より多く申告しているケースも考えられます。
このような場合に、あらためて土地の評価を行い、評価額を減額した上で請求を行うこともできます。相続財産に土地が多く含まれていた場合には、相続財産としての土地評価を行い、評価額が減額できる可能性がある場合には税額の還付を受けることも可能です。
他にも相続に関する手続きは多くありますが、2回にわたってお伝えした4つの内容は、クライアントだけでなく、他の相続人等も関わってくる手続きとなりますので、手続きを検討する場合には、事前に話し合いなどを行う必要があります。
このページのコンテンツを書いた相続士
- 相続士、AFP
1971年東京都生まれ。FP事務所FP EYE代表。NPO法人日本相続士協会理事・相続士・AFP。設計事務所勤務を経て、2005年にFPとして独立。これまでコンサルティングを通じて約1,000世帯の家庭と関わる。
相続税評価額算出のための土地評価・現況調査・測量や、遺産分割対策、生命保険の活用等、専門家とチームを組みクライアントへ相続対策のアドバイスを行っている。設計事務所勤務の経験を活かし土地評価のための図面作成も手掛ける。
また、住宅購入時の物件選びやローン計画・保険の見直し・資産形成等、各家庭に合ったライフプランの作成や資金計画のサポートを行っている。個人・法人顧客のコンサルティングを行うほか、セミナー講師・執筆等も行う実務家FPとして活動中。
FP EYE 澤田朗FP事務所
この相続士の最近の記事
 遺産分割2025.12.24相続財産に債務があり、相続放棄をする際の注意点
遺産分割2025.12.24相続財産に債務があり、相続放棄をする際の注意点 スキルアップ情報2025.11.26準確定申告とは?概要や必要な書類など
スキルアップ情報2025.11.26準確定申告とは?概要や必要な書類など スキルアップ情報2025.08.18相続と時効のお話 その2
スキルアップ情報2025.08.18相続と時効のお話 その2 スキルアップ情報2025.07.21相続と時効のお話 その1
スキルアップ情報2025.07.21相続と時効のお話 その1
相続士資格試験・資格認定講習のお知らせ

